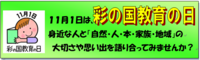本校保護者 様
お車での送迎は禁止しています
学校周辺は駐停車禁止です。送迎による駐停車は近隣の皆様のご迷惑になるばかりか、交通事故につながりかねない危険な行為です。
やむを得ずお車で来校する場合には近隣の有料駐車場をご利用ください。
なお、生徒の怪我や疾病等で車での送迎が必要な場合は、必ず担任までご連絡ください。
お知らせ
新着情報
4/21(日)
4/22(月)内科検診(3年)、文化祭実行委員会
4/23(火)心臓・結核検診(1年)
4/24(水)理数科オリエンテーション①、文化委員会
4/25(木)理数科オリエンテーション②
4/26(金)45分×6限、理数科オリエンテーション③、離任式
4/27(土)第1回学校見学会
保健だより「元気が一番!」4月号を発行しました。
春らしい気候が続く中、突然初夏のような暑さになったりと、新年度という環境の変化に加え、気温の変化も目まぐるしい日々が続いていますね。新しい環境での生活は何かと緊張が続くものです。身体も疲れやすくなりますので、疲れを感じた時は早めの就寝を心掛け、体調管理に努めてみてください。
4月号.pdf
授業が始まって早1週間が経とうとしています。
1年次の皆さんは高校生活、ならびに高校の学習に慣れたでしょうか?
本記事では授業中の風景をちらっと紹介します。少しでも雰囲気が伝われば幸いです。
3年次・数学
3年次・古典
2年次・英語
2年次・古典
2年次・数学
1年次・体育
1年次生は、初めての高校の授業で戸惑っている人も多いと思います。「高校は中学校の学習の上に積み重なる」と言われているものの、いきなり難しくなると感じている人も多いようです。学習リズムに慣れつつ、一歩一歩歩んでいきましょう。
2・3年次の皆さんも、昨年度よりもさらに発展的な授業となります。
しっかりと理解できるよう、授業に集中しましょう!
4/14(日)
4/15(月)内科検診(1年)、一斉委員会①
4/16(火)内科検診(1年)、一斉委員会②
4/17(水)
4/18(木)
4/19(金)内科検診(2年)、中央委員会、部長会
4/20(土)
以下の日程で第1回学校見学会を実施します。多くの方のご来校をお待ちしております。
日時
2024年4月27日(土) 13:00~16:00
企画内容
① 昨年度学校説明会動画上映 : 全体説明会・理数科説明会・普通科スポーツ科学コース説明会② 施設見学 : 時間内でしたら、自由に学校内を見学していただけます。③ 部活動見学: 部活動見学を実施する部活動は以下の通りです。
※ 急な変更がある場合があります。その際は学校HPにて告知させていただきます。
受付申込
参加には事前の申し込みが必要です。
こちらより申し込みをお願いいたします。
中学3年生の皆さんはもちろんのこと、中学1・2年生の方の参加も大歓迎です。
多くの方のご来校をお待ちしております!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遅くなりましたが、本年度の学校説明会・見学会案内が完成しました!
今回ご都合が合わなかった方も、ぜひ他の日程でご参加ください。
お待ちしております!
進路実績を更新しました。
詳細はこちらのページをご覧ください。
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
生徒会・部活動新着
今日で福岡インターハイへの1本道の第1関門である学校総合南部地区予選会が終了しました。
男子総合優勝!! 140点
女子総合3位! 101点
平成30年4月に合併して川口市立高校としてスタート切った6年前に総合優勝をしましたが、それ以来の男子総合優勝!女子も初めての100点越えでの総合3位を獲得しました。過去最高成績です!!
最終的には
優勝11種目、その他入賞35種目
県大会出場権獲得者 男子21名でのべ34種目、女子15名でのべ29種目
併せて男女4×100mリレーと4×400mリレーに出場します!
埼玉県大会(兼関東大会予選会)は5月12日(日)から15日(水)までの4日間、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場にて開催されます。県大会で6位入賞すると6月の関東大会(東京・駒澤)に出場権を関東大会で6位入賞するとインターハイ(福岡)への出場権が得られます。
ここから2週間強、関東大会目指し、自己ベストの更新目指して部員一同総力をあげて精進していきたいと思います。
3日間あいにくの天気の中、応援に駆けつけてくれた保護者やOB OG、競技会を運営してくれた皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました!...
4月23日に、関東大会県予選南部地区大会が行われました。この大会では、勝ちあがると5月に実施される関東大会県予選への出場権が得られます。本校は予選リーグで大宮南高校、市立浦和高校と対戦しました。
大宮南戦は、立ち上がりに2点を先取し、守備でも無失点に抑え、川口市立ペースで進みました。しかし、3-0で迎えた3回裏に1点を返され、続く4回裏に3点を追加され逆転をされました。最後まで諦めず戦いましたが、3-10で敗れてしまいました。
続く市立浦和戦では、2回表に5点を先制する最高の展開となりました。途中点差を詰められる場面がありながらも、全員で協力してリードを守りました。しかし、本校の見せた僅かな隙を突かれ、逆転を許してしまい、そのまま11-15で敗れてしまいました。この結果、関東大会県予選への出場権を得ることはできませんでした。
2試合を通して、非常にいいプレーが随所に見られ、冬の練習の成果を感じることができました。入部したての1年生も堂々とプレーすることができました。それと同時に、競った展開での我慢比べがこれからの課題であることも感じられました。3年生は、6月...
こんにちは、女子サッカー部です。
女子サッカーでは、男子サッカーと同様にU16(高校1年生世代+高校2年生早生まれ対象)トレセンが行われています。(*トレセン;トレーニングセンターの略。個人として優秀な選手たちを集め、トレーニングやゲームを高いレベルで行うことで成長を促すプログラム)
女子は、4月21日(日)に関東トレセンリーグ女子U16の第1節が群馬県で行われました。本校2年生早生まれの2名が3月のセレクションより活動に参加し、この度の第1節のメンバーとして選出されました。
<村上(2年スポ科・越谷市立光陽中学校出身)/宮島(2年スポ科・1FC川越水上公園メニーナU15出身)>
村上は、スタメンで起用され、ゲームキャプテンを任されるという大役も果たしました。そして、開始早々にチームを勢いづかせる先制ゴールを奪い、献身的な動きでチームに貢献しました。
宮島は後半開始から出場し、たくさんのチャンスを創り出し、こちらも1ゴールを決めチームの勝利に貢献しました。
トレセンリーグは、第2節、第3節と続いていきます。今回の活躍に安心することなく、今後もチームでの活動を通じて成長し、メンバーに選出され続けていっ...
こんにちは。女子サッカー部です。
早いもので、4月も中旬を迎え、学校総体埼玉県大会初戦があと少し、というところまで迫ってきました。
(初戦は、27日に開催されます)
3月下旬は、多くのチームとトレーニングマッチを行い、4月には鹿島ハイツで2泊3日の合宿を行いました。
その後もたくさんのトレーニングマッチを行ってチーム力を高めてきました。
(3月~4月上旬に対戦していただいたチーム)
文京学院大学女子高校(東京都新人戦2位)/クラッキスメニーナ(千葉県U15チーム)/埼玉栄高校/浦和西高校/杉並総合高校/甲府商業高校/山村学園高校/戸塚FCガールズU15/春日部市立武里中学校サッカー部(男子)/浦和第一女子高校/大宮アルディージャVENTUS U18/八千代松陰高校(千葉県)/秋草学園高校/和光国際高校/常磐大高校(茨城県)/弥栄高校(神奈川県)/杉並FC U18(東京都)/ふたば未来学園高校(福島県)/浦和実業学園/東大和高校(東京都)/幕張総合高校(千葉県3位)
女子サッカー部では嬉しいことに、多くの新入部員を加え、大所帯となりました。これから始まる学校総体こそは『優勝』を手にできるように、チーム一丸となって戦っていきます。目...
本日22日(月)から24日(水)までの3日間、上尾運動公園陸上競技場で行われている福岡インターハイに繋がる「学校総合南部地区予選会」1日目の速報です!
男女5種目で優勝!!
男子4×100mリレー(1走野田、2走小田、3走金子、4走宮北) 41"74
男子1500m 古澤空 4'04"14
男子走幅跳 野田七星 6m74(+1.8)
女子1500m 池田美咲 4'38"48
女子やり投 長井花音 43m65
その他、男女合わせて8種目で入賞9、県大会出場権獲得者17名
朝から雨が降る天候でしたが、だんだんと雨も止み、良いコンディションの中での大会でした。
今年の4月から本校体育科に転勤してきた短距離専門の小縣良平先生の力もあり、男子4×100mリレーで優勝できたことは、明日以降の戦いに良い流れを引き寄せることができました!
残り2日間、全員陸上で頑張りたいと思います!
応援よろしくお願いします!!
男子4×100mリレーで優勝したメンバー(左から1走野田、2走小田、3走金子、4走宮北)
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.RoomsLanguage.display_name}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}