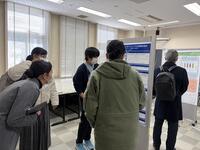SSHの取り組み
【SSH】理数科1年次物理地学特別講座「虹の不思議~スペクトルでわかる宇宙~」
2/19(木)、理数科1年次を対象に本校坂江教諭による物理地学特別講座を行いました。
一人一台の直視分光器で蛍光灯、太陽光、LED灯、Naランプの光を観察し、それぞれスペクトルがどうなっているか観察し、スペクトルとは何かについて学びました。
その後、坂江教諭の高分散分光器を用いて、ナトリウムの炎色反応を観察し、吸収線の原理を学びました。最後は、虹の人工的な発生道具として、プリズムと回折格子による光の分光を観察し、今日の講座を終えました。
坂江先生、ありがとうございました。
【SSH】ハワイ大学マノア校 Dr.Matthew Knope オンライン講義
2/18(水)、理数科2年次生がハワイ大学マノア校教授、Matthew Knope 氏のオンライン講義を受講しました。
これは、11月のハワイ研修でKnope先生の体調不良により急遽中止となった講義を代替して実施いただいたものになります。タイトルは「Origin and Evolution of the Hawaiian Island」。ハワイの島々の起源と火山活動について、約1時間の講義をして頂きました。本校CIRも3名参加し、質疑応答で生徒たちに模範を示してくれました。終わりには、生徒会副会長・天文部部長であるN君から、お礼の言葉を英語でKnope先生に送りました。
また、オアフ島での活動を様々にサポートしてくれた、ハワイ東海インターナショナルカレッジのCodyとの再会も、生徒たちにとって貴重な時間でした。最後には「See you again in Hawaii!」とメッセージを送ってくれました。
【生徒の感想】
・火山の活動で私たちが見られる部分というのは全体のほんの一部に過ぎないと思った。単に噴火するにも地中の核だったり、熱やマグマだったり色んなものが関わっているので目に見えない部分まで考えると見えている部分の何倍も話が壮大なものなんだと分かった。
・ハワイの火山がプレートが動くことによって形成されたことや、火山の種類について知ることが出来た。写真が多くてわかりやすかった。英語の発音だったり話す速さに徐々に慣れることが出来て、リスニングの練習にもなった。
・難しい内容だったが、今までの知識を使って情報を補填しながら講義を受けることができたので良かった。ハワイ研修から少し時間が経った中での講義で忘れていた内容も思い出せるような講義で楽しかった。
・研修旅行の時に聞いた内容も踏まえて何となく知っていることも多かったけど、他の火山との比較やハワイの言葉(pahoehoe, 'A'a flow)など新たに知れたこともあったし、英語での講義で全部を聞き取ることはできないけれど、聞き取れた言葉やパワーポイントから内容を予測することもできていい経験になった。
・ダミアン先生(注:本校CIR)の質問の仕方を見ていて、どのような質問の入り方がいいのか、相手に話しかけるときの動作を学べました。
【SSH】川口市立医療センター「ダヴィンチ」体験会
1/17(土)、川口市立医療センターで本校生徒対象の「手術支援ロボット ダビンチXi 体験会」が行われ、14名の2年次生が参加しました。多くの職員の方々にご対応いただき感謝申し上げます。
これは、川口市立医療センター様より医療職の魅力や興味関心を高め、将来の進路の選択肢としてもらえるような体験型イベントとして企画頂いたものです。当日はダビンチ体験に加え、腹腔鏡体験、手術室体験、また特別講演をして頂きました。
普段なかなか入ることのできない医療の現場に足を踏み入れて、実際にアームを動かして最先端医療技術に触れる貴重な体験をすることができました。
川口市立医療センターの皆様、ありがとうございました。
【生徒の感想】
・ダビンチの性能の高さに驚いた。まだ、外科か内科で迷っているが、AIのアシスタンスなどが追加されていることから、若干自分の意思が外科に傾き始めた感じがあった。頑張って勉強して医学部に入りたい。
・医者とバイオ研究者などで職業選択の迷いがあったのですが、手術や機械操作などの医療体験を実際にやってみて、集中力と体力、忍耐力がいることが分かり自分に医者になることはやっぱきついかもしれないと改めて感じた。職業選択において非常に有意義な時間でした。
・医療関係者の方々が優しく丁寧に教えてくださりとても学びになりました。また、実際にAIを使ってみて医療の不足分をAIで補っていき、医療の正確性の向上が感じられました。今回の体験を通して、自分が医療現場で働くイメージ像が少しだけ湧いてきたと思います。本当にありがとうございました。
【SSH】令和7年度理数科2年次課題研究発表会
2月6日(金)、理数科2年次生が課題研究発表会を行いました。
5月のテーマ発表会から9月末の中間発表、そして11月のハワイ英語発表を経ての最終報告会となります。最初に立てたリサーチクエスチョンからそれぞれ研究を進め、タイトルも新たに5名のSSH運営指導委員の先生方、理数科1年次生、来場した保護者の皆様、本校教員に向け発表をしました。
今回は初めて昨年3月に卒業した理数科OBも3名来場し、後輩たちの発表へ質疑応答でエールを送ってくれました。運営指導委員の先生方も、各研究に対して丁寧な指導助言をして頂き、まとめの論文作成に向け新たな刺激を受けることができたのではないでしょうか。
ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。
【SSH】探究学習合同発表会@東京都立大学
1月31日、東京都立大学南大沢キャンパスにて行われた第6回探究学習合同発表会に、中高一貫生1.2年次生から3名が参加しました。 本校からは初めての参加になります。
今回参加した研究タイトルは
・渋切りによる小豆の鉄分吸収への影響〜阻害物質タンニンの除去を目指して〜(化学)
・筋電を利用した入力インターフェイスの作成(工学①)
・弓道フォーム解析のための映像人体抽出と動作比較プロセスの提案(工学②)
です。埼玉県からの参加は本校のみでしたが、初めての参加で東京・神奈川・千葉・山梨の多様な県の高校生の研究発表に触れ多くの事を学び、また共通のテーマでの探究をしている生徒同士の交流も作ることができました。
【SSH】令和7年度 探究活動生徒発表会
12月25日に日本薬科大学にて行われた埼玉県探究活動生徒発表会に理数科2年次と中高一貫生1、2年次の希望者5名が参加しました。
この発表会は県内から50を超える学校が一堂に集まり、探究活動の成果発表を行うものです。
本校は昨年に引き続き、口頭発表2チーム、ポスター発表4チームが参加しました。
どの発表もこれまでの取り組みの成果をしっかりとまとめ、発表していました。創意工夫を凝らした検証やポスター、発表により多くの参加者の皆様からコメントや質問をいただくことができ、今後の活動に向けて収穫の多い発表会になりました。
自身の発表以外でも、他校の探究活動についてたくさんの発表を見ることができ、高校生でもこれだけのことができるということや、高校生らしいユニークなアイデアに触れることができました。
たくさんの刺激を受けることができ、今後の探究活動へのモチベーションも上がった1日となりました。
【SSH】理数科2年次ハワイ海外研修報告
12/24(水)、2学期終業式後の報告会において、3名の理数科2年次生徒が11月に実施したSSH米国(ハワイ)海外研修の報告を行いました。
それぞれがこの研修で「体験」し、「感じ」、「学んだ」ことを各自の言葉で全校生徒に向けてプレゼンし、成果の共有を図りました。実際に現地に行って体験することの大切さを、生徒みんなに伝えてくれました。
この報告の前には、フィンドレー市からの留学生2名が同じ高校生として、日本で過ごしたことの体験と私たちは同じ世界の「仲間」なんだ、という素晴らしいスピーチをしてくれましたが、それとともに本校の教育における「国際性の育成の深化」に、資する時間となったかと思います。
【SSH】東京大学医科学研究所訪問
12/22(月)午後、希望者8名(普通科・中高一貫生2年次6名、特進1年次1名、理数科1年次1名)で白金台にある東京大学医科学研究所を訪問しました。
今回は、システムウイルス学分野の佐藤研究室を訪れました。佐藤研は、先の新型コロナパンデミックにおいて日本のウイルス研究をリードしてきたラボです。
まず特任研究員の瓜生慧也様から、システムウイルス学研究室の概要、どのような研究をしているのかというコンセプト、新型コロナ期における世界と日本のウイルス研究の状況などを講義して頂きました。先のパンデミックで日本におけるウイルス研究者の不足がはっきりし、ぜひ高校生にこの道に進んで次のパンデミックから人類を守ってほしい、と生徒たちにメッセージを送って下さいました。
続いて特任研究員臼井郁様から、「ウイルス研究におけるフィールドワーク」と題して講義を頂きました。もともとコウモリの進化を研究していた所、コロナウイルスはコウモリをメインに宿主にするということからこのシステムウイルス学研究室に来て、様々な分野を学際的に研究するというお話をしてくださいました。生徒の事前質問にも、色々なことを多様に学んでいくことが大切であるとお答えいただきました。
先日の荏原先生のご講演を聞いた2年次生は、その繋がりでまた研究者から深く学ぶことができたのではないでしょうか。年の瀬のお忙しい中に訪問を受け入れて下さった皆様、ありがとうございました。
【SSH】理数科つくば研修で訪問している研究者にご講演いただきました
12/19(金)、2年次「アントレプレナーシップ講演会」において、理数科1年次つくば研修で訪問しているNIMSより、荏原充宏先生を講師にお迎えしました。
荏原先生は、NIMS(物質・材料研究機構)にてスマートポリマーの研究をしており、本校理数科では一昨年より研究室訪問をさせて頂いています。今回の講演は、そのときにお話を聞いた教員が「ぜひ多くの生徒に聞かせたい」と思った「志」によって実現しました。今年度のつくば研修にてその教員が再び荏原研究室を訪れ、本校SSH運営指導委員長である中部大学井上先生のサポートの元、今日を迎えることができました。
「人が想像できることは人は必ず実現できる」というジュール・ヴェルヌの言葉を皮切りに、研究とは、研究者とは、そしてそこの事をどのようにして世の中に役立てていくか。多くのことを2年次の全生徒に向けて話して下さいました。質疑応答では時間内に収まらないほどの生徒が手を挙げてました。
講演終了後は、事前発表をした生徒8名+飛び入り1名で懇談会を行い、より深く研究者としての荏原先生と「対話」を行い、多くの学びを得ることができました。今回の講演を通して、理数科の生徒が行ってる本校SSHのテーマである「研究者との対話」を普通科の生徒にも広げることができました。
荏原先生、ありがとうございました。
◎今年のつくば研修で荏原研究室を訪問した理数科1年次生の事後学習ポスターです⇒スマートポリマーについて~荏原先生から学んだこと~.pdf
【SSH】分子生物学会参加
12/5(金)、パシフィコ横浜にて行われた分子生物学会高校生ポスター発表に自然科学部と中高一貫2年次生1名が参加しました。本校からは3年前に理数科2年次生の課題研究班が参加しており、それ以来の発表になります。
当日は、高校生だけではない本物の学会の中でたくさんの研究者に対して発表を行いました。
生徒はたくさんの研究者の皆様から温かいコメントをいただくことができ、今後の研究に一層力を入れて行きたいと決意を新たにしたようでした。
これからも様々なコース、部活での探究活動を進めていきます。応援よろしくお願いします。